【※この対談は、2015年4月8日発行のスパイラルペーパーno.138に掲載されたものです。】
表現としての焼物の魅力
2014年に開催した「SICF15」にて、日常の品をモチーフに本物と見紛う程の精度で陶土を手彫りし焼成した作品『存在の感触』でグランプリに輝いた山本優美さん。一方、磁器に古今東西の文様から紡ぎだした独自の物語を超人的な技術で緻密に描く美術家・葉山有樹さん。陶を素材に全く異なるアプローチで向き合う二人が制作に対する姿勢や想いなどを、雪がしんしんと降り積もる金沢卯辰山工芸工房で語り合いました。
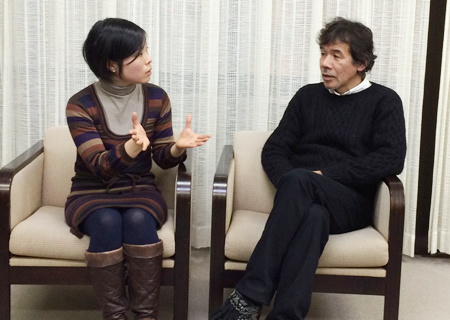
山本優美 アーティスト
1983年大阪生まれ。2007年 金沢美術工芸大学美術学部工芸科 陶磁専攻卒業、2009年ベルギー国立ラ・カンブル美術大学修士課程修了、2013年金沢卯辰山工芸工房技術研修修了、現在石川県金沢市で制作を行う。
葉山有樹 陶芸家
1961年佐賀県有田町生まれ。1985年葉山有樹窯を開窯。 2007年にスパイラルで行なった個展がヘルシンキのデザインミュージアムへ巡回。2012年グループ 展「工芸未来派」(金沢21世紀美術館、石川)参加。
インタビュー
- お二人は、作品へのアプローチは異なりますが、制作の最後は「焼く」という自然の現象に委ねて完成とする特殊な性質を持つ焼物を素材に作品を作られていますね。
山本:私は、もともと欧米の美術に興味があり、空間や立体を構成するアートをやりたいと思っていました。様々な素材に触れたいと思い、大学では工芸を専攻しましたが、学ぶうちに工芸と、アートの世界では価値観が違うと感じるようになりました。そんな中、陶芸がアートの文脈でどんな意味を持つのだろうと考えたとき、焼物のプロセス(柔らかい土が焼く事により堅くなり形を留めること)と時間とのつながりに興味を持ち、そこに陶芸独特の意味があるのではないかと考えるようになりました。
葉山:そうですね、焼き物はものづくりの中でも数少ない、最後の仕上げを自然の力に委ねないと成立しないという特性があります。僕は絵付けを主として行ないますが、焼物の塗料は全て鉱物を使用しているので、制作の最中に目に見えている色と焼成してあらわれる色は、経験の範囲ではわかっていますが、焼き上がるまで正確にはわからない。制作過程にコントロールが利かない部分があるということはもどかしい思いもしますが、手が届かない世界が存在するとも言え、そこが焼物の魅力だとも思います。山本さんは、なぜ陶器でこれらの作品を制作しようと思ったのですか?
山本:私は、日常的に目にしているイメージを変質させ、手を加えることによって新しい視点を与えるきっかけを創出したいと考えています。陶器が時間の経過によって変化する素材だと意識し始めた時から、焼物を「記憶のメディア」として捉えています。その焼物で人の記憶や営みと関わりのあるものをモチーフに作品を作りたいと思うようになり、あるとき、記憶を連想させるハンカチの束をモチーフに作品を制作しようとしました。しかし、ハンカチは柔らかいので型が取れません。そこで、実物を見ながら粘土を彫ることにしました。完成した作品を見て、布という柔らかい印象を与えるものが焼物になって固まってしまうという変化がとても面白く、その後、衣類などの柔らかさを連想させるものを通じて人間の存在感を陶器で表現することに意味を感じるようになりました。
葉山:焼物といっても色々あるし、彼女がやっていることは近年でてきた新しい表現で、僕も見たことが無いような、陶でこんな柔らかい質感が出るんだという驚きもありました。焼物ですから匂いなんてないのですが、このくつ下(『存在の感触ー靴下ー』)なんかは、それすら感じるようなリアリティだけではない何かを感じさせる所に作者の想いがあり、愛情をもって作られているのを感じます。

「SICF15」グランプリ受賞作『存在の感触ー靴下ー』
山本:私たしかに、私が作っているものは、触覚を刺激するようなものが多く、手作業で制作される素材のリアルな感覚や感触は工芸の一つの魅力だと思います。本来の機能は失われても、そのものが持つ思い出や記憶の強さや濃密さなど、焼物の表情から実物を見ることとは異なる視点を与えたいと考えています。私の作品に対し、超絶技巧と評価してくださる方もいらっしゃるのですが、リアルさや技術は自分が表現したいことへ到達するための手段であり、結果としてあらわれるものだと思っています。
葉山:そうですよね、人間の手でやることだから、リアルさをとことん追求するよりも、作者の想いを形にする事が重要だろうと考えています。現代の価値のみならず、将来を見据えた物づくりも面白いと思いますよ。僕も超絶技巧とか言われるけれど、それはまわりの評価でしかなく、本人はそんなこと思わないよね。
作品に込める想い
- 作品に込められた時間や想いが凝縮されていればいるほど「儚さ」という概念が作品に現れる印象があります。何を思って制作に取り組んでいるのでしょうか。
山本:制作中は、モチーフとなる衣類を身に着けていた人の存在を想いながら、尚かつ自分の時間も編み込んでいくような感覚がありますね。作業的にやっている訳ではなく、服を通して向こうにいる人の存在を思いながら手を動かしています。葉山さんはどうですか?
葉山:僕の場合は「精神と時の部屋」と呼んでいる作業部屋に籠ります。正に、漫画のドラゴンボールに出てくる通り、そこに入って仕事は通常とは異なり驚異的な集中力とスピードで作業する事が出来ます。ただ、出てくるとすごく老化している(笑)。我が身を犠牲にして、どうなってもいいという覚悟で制作に取り組んでいます。でも、人間って自分の為だと頑張れる度合いに限りがあるんですよ。だけれど、誰かの為ならできてしまう。僕の制作のモチベーションを保っているのは、亡き母に向けてという想いが強い。母は、社会の中でも恵まれず、大変な苦労をして最期を迎えました。亡くなった人は蘇らないけれども、社会の不公平さ、理不尽さをそのままにしておけない、と常に考えています。その人が生きた痕跡を自分の手を通して残せるように、一本一本の線に想いを込めています。常に自分が持っている最高以上の力を出すつもりで仕事をしています。
山本:常に全力ですと、何をもって作品の完成とし、焼成へ移るのでしょうか。
葉山:制作に着手する前は考えたり、悩んだり、リサーチをしたり、描き始める前に膨大な時間を掛けますが、筆を持った時点で完成形が見えています。躊躇すること無く、これが最善なんだと確信に満ちていなければ生きた線なんて描けません。また、工程を重ねる中で、描き過ぎないよう我慢することも大切です。全ての作品ではありませんが、「この作品は、時間の力を借り、数百年の時を経た姿が完成である」という考え方に基づき制作する時もあります。
山本:時間の流れで考えると、私は近い過去・現在を見ているのかもしれません。「SICF15」でグランプリを受賞した『存在の感触』は、同時代を生きている人の存在を作品として留めることがテーマでしたが、作品として完成したときに、風化したような、ある種の哀しさが表情としてあらわれます。その後の「SICF15グランプリアーティスト展 うつしみ」では、戦争中に青春を過ごした祖母の思い出がつまった品をモチーフとし、現在と過去がつながり浮かびあがってくる作品を制作しました。この作品では厳しい時代を生き抜いてきた女性の姿を通じて、人間の存在の孤独さだけでなく、強さや温かみへとアプローチできたように思います。葉山さんがリサーチに膨大な時間を割くように、モチーフを選択し制作、完成するまでの私の中でのストーリー性を今後考えていきたいと思っています。
- 山本さんは、今年5月の「SICF16」と同時期開催の「SICF15受賞者展」で新作を発表しますね。
山本:今回出展する作品は、100年ほど前に製作され、身に着けられていたレースをモチーフにしています。日ごろ衣類を観察する中で、レースや刺繍といった細部には身に着けていた人の思いが一層強く籠っているように感じてきました。時間と空間を越えて、また現代に生きる私の時間と身体を通じて、美しいレースに込められた人々の存在や記憶を今日も色あせない感覚として甦らせたいと思います。
次回「SICF」に向けて
- 「SICF16」からも次代を担うであろうクリエーターが数多く登場してきます。彼らに向けて、ものづくりを続けていく上で葉山さんが心がけていること、アドバイスなどがあれば教えていただけますか。
葉山:自分が何を成すべきかということをきちんと考えて、がむしゃらに臆することなくやっていって欲しいと思います。人間って地位とか名誉とかお金とか、どうでもいいことに気をとられがちですよね。はっきり言って、有名になるなんて、どうでもいいことなんです。それよりも自分が納得できる仕事ができているか、そこだけをぶれずにしっかりとやってもらいたいと思います。その姿を誰かが必ず見つめていますから。
聞き手:近藤恭代(金沢芸術創造財団)




